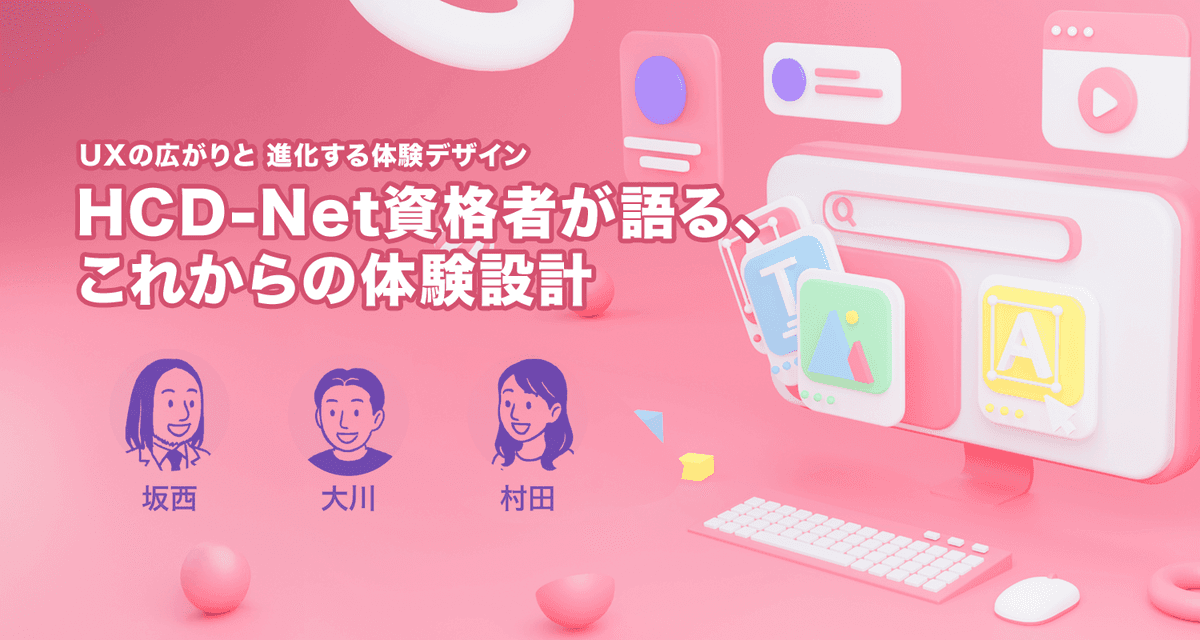UXの広がりと 進化する体験デザイン——HCD-Net資格者が語る、これからの体験設計

こんにちは。シナップ大川です。
今回はシナップの活動報告も兼ねた小冊子『SINAP Journal 2025 Summer』に掲載した「UXの広がりと 進化する体験デザイン——HCD-Net資格者が語る、これからの体験設計」の記事をご紹介します。
シナップには、HCD-Net認定の人間中心設計(HCD)専門家・スペシャリストが在籍しており、日々のプロジェクトの中で、実践的なUXデザインを追求しています。
今回はその中から、坂西・大川・村田の3名が登場。それぞれの経験をもとに、現在のUXデザインの現場感や、これからの体験設計について語り合いました。
※ 人間中心設計専門家、人間中心設計スペシャリストとは
人間中心設計推進機構(HCD-Net)が実施する専門家、スペシャリストの認定制度で、日本におけるUX/HCD分野のプロフェッショナルとしての知識・経験を証明する資格です。特に専門家はプロジェクトでの中心的な推進役としての経験が必要とされ、「プロジェクトで主導的な役割を果たせること」が認定基準となっています。

UXって 〝当たり前〟になってきた !?
大川:最近、お客様の中でも「UX」という言葉が浸透してきていると感じるのですが、実際どう感じていますか?
村田:かなり普及していると感じます。以前は「このプロジェクトではまずUXリサーチを行いたいのですが…」と説明が必要でしたが、最近は先方から「ぜひ進めたい」と仰ってくださるケースも増えました。ただ、UXリサーチ自体が目的になっている場合や、そうではなくとも、実施後の成果、具体的な手段まではご存じないことが多いです。
坂西:確かに言葉は浸透したけど、ウェブサイトやアプリを〝作りたい〟という要望の背景にある「なぜ」を掘り下げる過程で、ユーザー理解の重要性をご理解いただき、そこからUX専門家が関わるケースもまだまだ多いと感じています。
大川:言葉は知られるようになってきたけれど、実際の進め方や考え方まではまだこれから。だからこそ、こちらからの提案や実施内容を丁寧に伝えていくことが大事ですね。
HCDプロセスの理想と現実
大川:本質的という意味では、HCDプロセスは、本来、仮説と検証を繰り返す継続的なサイクルが前提ですが、実際どこまで回せていると感じますか?
坂西:答えづらい質問だなぁ(笑)、ご相談いただくことの中ではやっぱり「作ること」が目的なことが多いので、リサーチなども「作るため」に行われて「作ったら終わり」になってしまうことも多いですね。プロジェクトごとのスピードやフェーズごとの目的も異なるので一概には言えないけど、当初の仮説を検証して適応していくことや、より深く顧客を理解していくことがビジネス的な価値につながるということを、うまく伝えられていないという不甲斐なさは感じています。
村田: 私もそう思います。リリース後にはデータも取れるようになるので、それをもとに、シナップでやっている「グロース支援」みたいな継続的なアプローチに発展させていけると理想的だなと感じています。
「UXやってます」って言う会社、多いけど…選ぶの難しくないですか?
大川:「UX」という言葉が普及し、「UXに取り組んでいます」と掲げる会社も非常に増えてきました。シナップもそのひとつですが、お客様がそういった会社を選ぶ際、違いが見えづらく、選定が難しいのではないかと感じます。
坂西:UXは課題を一緒に見つけていくプロセスで、事前に成果物を提示することもできないので違いを判断するのは難しいですね。基本は課題に対してどう向き合い、どんな結果を出してきた会社や担当者なのか?実績を通じて語ることが大事だと思います。
村田:リサーチ手法自体は誰でもある程度再現できますが、結果をどう解釈し提案に落とし込むかが各社の違いです。企業選定時に差別化ができるとしたら、自社の専門性や実績を示すことだと思います。
外部専門家を活用する真価
言語化と組織変革
大川:「リサーチ手法自体は誰でもある程度再現できる。」という話がでましたが、外部の専門家を活用するメリットとは?
村田:第三者の視点で言語化して共有することも大きいと思います。どのご担当者様も、ひとつのWebサイトだけを見ているわけではないため、気になっている箇所はあれどまとまった時間が取れずおざなりになってしまうことが多いと思います。外部に依頼できれば時間を確保しなくても課題の可視化が進み、かつご自身では言語化できなかった課題感がプロ目線で解説・チーム内で共有できますので、組織の意思決定に貢献できると考えています。
坂西:まさにそれがUXデザインがもたらす副次的な価値だと思います。プロジェクトメンバーが多くて意見や方針をまとめるのが難しいような時に、調査結果やそこから出てきた課題や解決策、ロードマップを資料に落とし込んで共有することで、目線が揃って動きがよくなったり、サブプロジェクトがどんどん生まれて大きな波及効果を生み出していく、という状況を何度も見てきました。
大川:そこは僕も同感です。こうした副次効果はもっとアピールしていきたいですね。
UXデザインとAIのこれから──変わる意思決定と情報設計
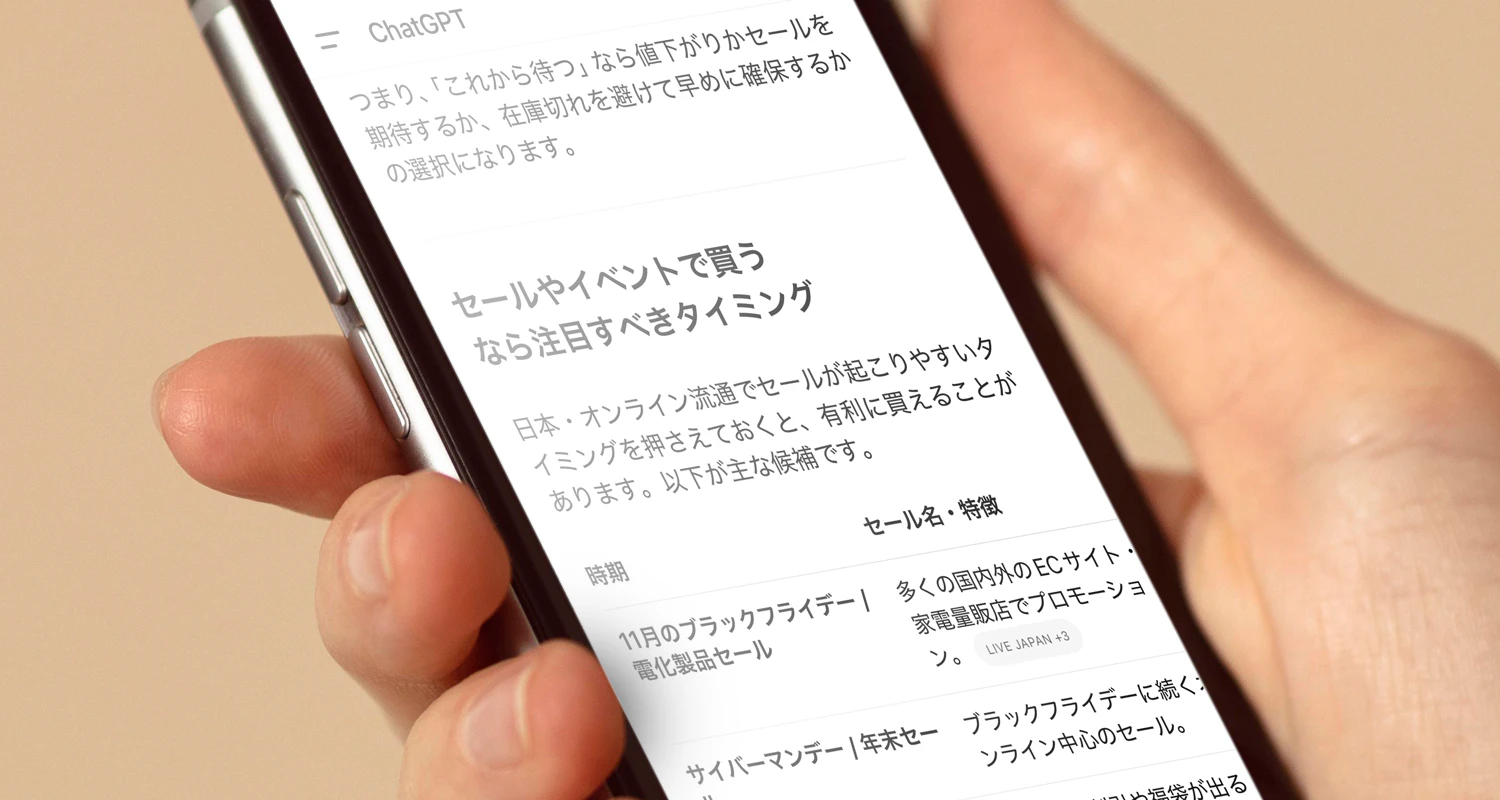
大川:最後に、AIがUXに与える影響についてどう思われますか?
AIがユーザーの意思決定に深く関わるようになり、従来のカスタマージャーニーマップも見直しが必要になるのではと感じています。
村田:検索よりもAIを介した情報取得が主流になれば、従来のジャーニー設計はまた大きく変わりますよね。
坂西:AIによる変化は非常に大きいですね。ユーザーの情報収集能力が一気に高まり、企業の評判や記事の質が可視化され、評価されやすくなります。
また、UIに関しても、今後はユーザーの状況に応じてその場でAIがUIを生成するような体験が当たり前になるかもしれません。最終的に求められるのは「ページ」ではなく、ニーズに合わせて読み書きできるデータやAPIになっていくでしょう。
大川:提供側も変わってきますよね。
村田:私たちUXを設計する側としても、AIを使ってペルソナの妥当性を検証したり、ジャーニーマップの抜け漏れ確認や補完にすでに活用しています。
坂西:リサーチの現場でもAIの活用は進むよね。データの集計・分析などではAIのパワーを活かして大きな変化が生まれてるし、インタビューでも、人格を与えたAIをペルソナとして扱うことで、複数のユーザーインタビューを同時に時間の制約なく行うようなことも可能です。またリサーチ後に、それらの調査データを学習したAIと一緒に戦略考えるとか、わかりやすいところでは、コピーやUIなどの具体的なコミュニケーションを考えていくシーンでも、大いに使えそうです。
大川:AIの進化は、ユーザー行動とデザインプロセスの両方に大きな変革をもたらしそうですね──。
今日の座談会を通して改めて感じたのは、やはりUXは時代と共に変化していくもの。だからこそ、継続的に改善していくことが重要だと思いました。
これからも柔軟に学び続けながら、よりよい体験のあり方を追求していきたいと思います。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。本対談では、「UX」が当たり前になりつつある今、HCDのプロセスを本質的に回していくことや、AIを取り入れた新たな体験設計の可能性について、資格を持つ専門家だからこそ語れる、現場のリアルとこれからの展望が語られました。
シナップには、HCD-Net認定の専門家・スペシャリストをはじめ、豊富な知見を持つUXデザイナーが在籍しています。UXリサーチから課題改善のご提案、具体的な制作まで、一貫したご支援が可能です。実際のUXリサーチやUXデザインのアウトプット資料の具体例をご覧いただくこともできますので、ご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。